内分泌に関する研究
近年の内分泌学においてホルモンは、古典的な細胞間の情報伝達だけにとどまらず、神経系、免疫系などとも大きく関連し、生体内全ての細胞および臓器が様々な情報交換を行いながら、生体の維持に寄与していることが分かってきている。つまり内分泌を学ぶことは“生体の恒常性の全てにおいて学ぶこと”とも言える。
内分泌疾患の臨床においては、生化学・画像検査の進歩により、原発性アルドステロン症をはじめ、様々な内分泌疾患の鑑別を要する症例が増えていている。各疾患の原因については遺伝子レベルでの病態解明も進み、診断におけるデバイスや様々なホルモン製剤の開発など治療の選択肢も増加しており、より専門的な知識と経験が求められる時代となりつつある。また、脳神経外科や泌尿器科といった他診療科との連携も重要であり、ホルモン産生腫瘍の周術期管理はもちろんのこと、不妊症・不育症の診療における甲状腺機能異常や性腺機能低下など、産婦人科との連携も必須である。さらには、様々な癌治療に適応となった免疫チェックポイント阻害薬は、自己免疫性甲状腺炎や下垂体機能低下症などの内分泌分野での副作用も多く出現することが分かっており、癌治療の領域においても内分泌医専門医の活躍の場が拡がっている。
古典的な内分泌疾患に関する診療だけにとどまらず、近年は、ホルモンと生活習慣病との結びつきに注目が高まっている。例えば、成長ホルモン(GH)と生活習慣病との関連は良く知られているが、当教室ではGH抵抗性に関して注目し、臨床研究を進めている。また、アルドステロンは原発性アルドステロン症でなくとも肥満患者でも増加するアルドステロン合成促進機序が分かってきており、さらには、生活習慣病の病態基盤に、アルドステロンとは独立したミネラルコルチコイド受容体(MR)の活性化機序が示唆されており、MR拮抗薬が糖尿病合併症予防の創薬のターゲットとして期待され、当教室でも研究を進めている。
当医局は附属4病院を合わせると、日本でも有数の糖尿病患者数を誇っており、どの研究班に所属していても、糖尿病診療の経験を十分に積むことができる。その中で、当研究班は内分泌医としての視点も育み、経験を積みたいと思う医師を求めている。
主な研究テーマ
1. 基礎研究
・糖尿病におけるミネラルコルチコイド受容体に関する研究
糖尿病を代表とするインスリン抵抗性を基盤とした病態では、内臓脂肪の蓄積によりアルドステロン分泌増加が生じている。一方で、高血糖などを介した機序により、組織レベルでのMRの活性化も生じていると考えられている。こうした生活習慣病におけるMRの働きについて研究している。
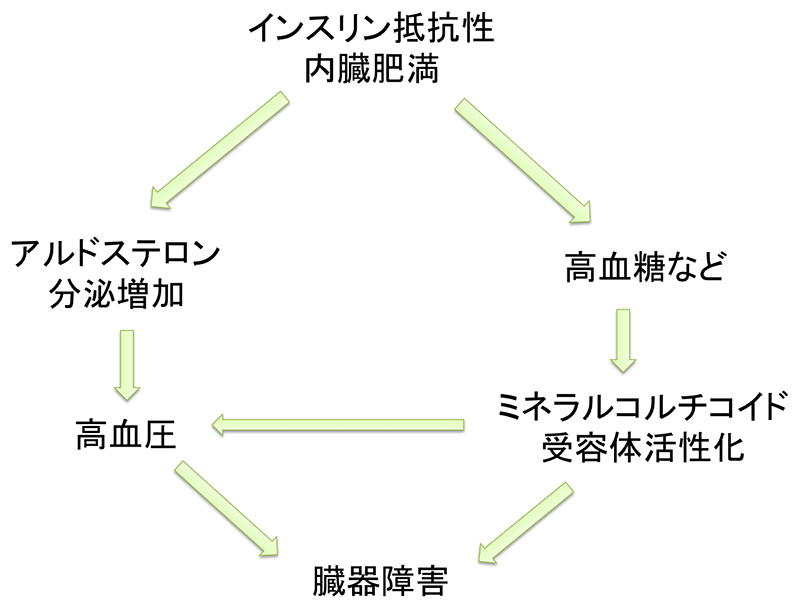
・下垂体腫瘍の病理学的分類と臨床所見の関連についての検討(国内留学)
2. 臨床研究
・下垂体機能異常患者の実態とその機能の評価、その後の補充療法に関する調査:SS-MIX2を使用した患者データベース研究
・原発性アルドステロン症に関する後方視野的検討
・糖尿病における成長ホルモンの役割について
・糖尿病の急性合併症におけるバソプレシンの役割について
・糖尿病合併症おけるミネラルコルチコイド受容体拮抗薬の効果に関する研究
・高速液体クロマトグラフィー(HPLC)法による内分泌疾患における脂質プロファイルの分析(国内留学)
・内分泌疾患患者のデータベース 内分泌患者数(2018年度 カルテベース)
| 本院 | 葛飾 | 第三 | 柏 | |
|---|---|---|---|---|
下垂体疾患 |
160 |
60 |
30 |
45 |
甲状腺疾 |
1470 |
550 |
150 |
250 |
骨代謝・副甲状腺疾患 |
50 |
15 |
20 |
25 |
副腎疾患 |
275 |
60 |
40 |
80 |
性腺疾患 |
15 |
3 |
3 |
5 |
その他 |
20 |
1 |
― |
5 |
・稀少症例に関する症例報告
チーフ
| 講師 | 山城 健二 |
| 講師 | 大橋 謙之亮 |
受賞
- 2024年 日本内分泌学会関東甲信越支部学術集会 会長賞(春日 英里)
- 2023年 日本糖尿病眼学会 福田賞(大橋 謙之亮)
- 2023年 臨床内分泌代謝Update 優秀ポスター賞(春日 英里)
- 2022年 日本内分泌学会関東甲信越支部学術集会 会長賞(第三病院研修医)
研究助成
- 2025年 文部科学省科学研究費補助金 若手研究(大橋 謙之亮)
- 2024年 東京慈恵会医科大学同窓会 海外派遣助成(辻本 裕紀)
- 2023年 日本甲状腺学会 トラベルグラント(辻本 裕紀)
- 2023年 東京慈恵会医科大学大学院 研究助成金(辻本 裕紀)
留学先
- 森山記念病院